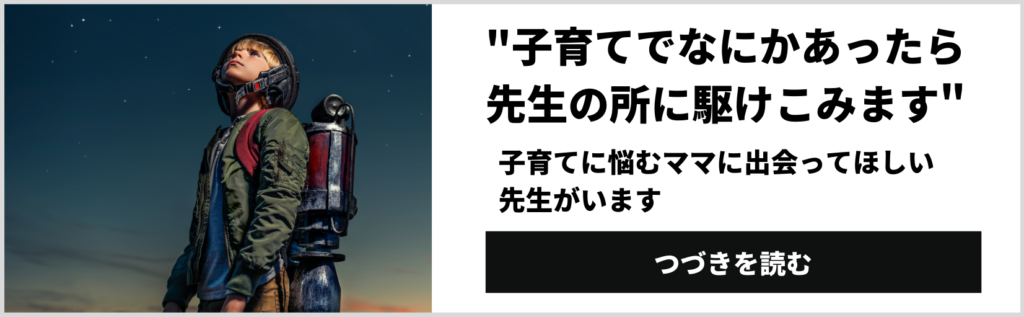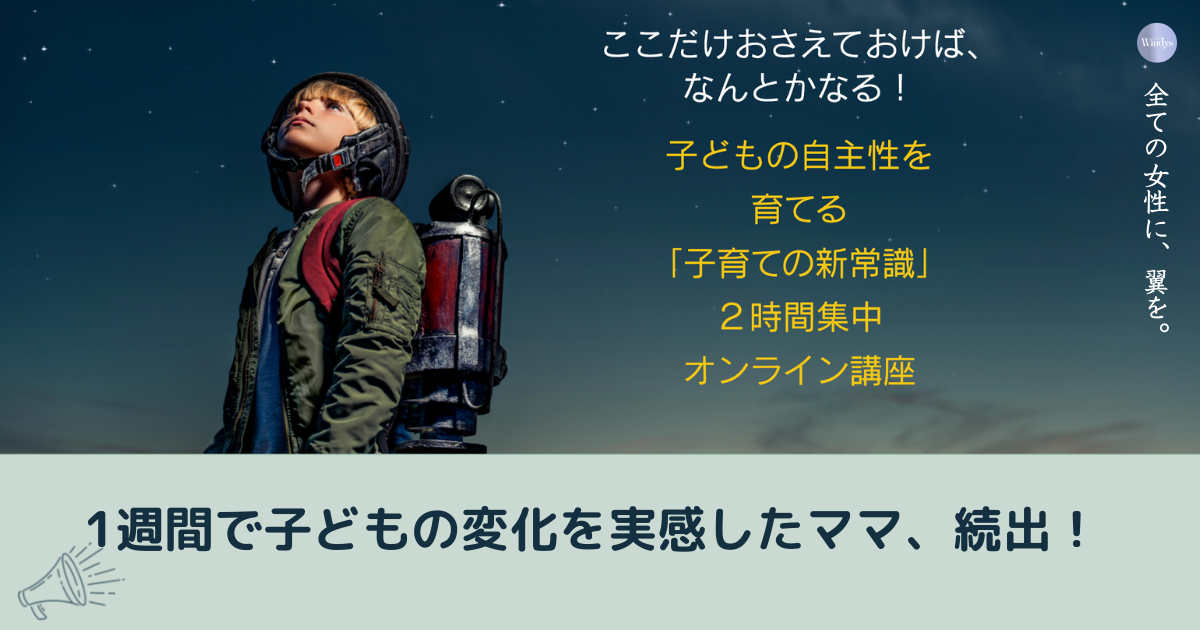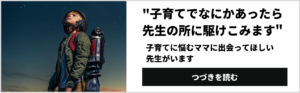「水野谷塾」って?という方はこちらからどうぞ!
=============
これからお子様が小学校に入学される親御様にプレゼントです!
「子どもが主体的に行動するようになる秘訣」をお伝えします。
なんでもはじめが肝心!
親御さんが肝に銘じることは、
『先導しない』
ということです。
「これ、やった?あれ、やった?」と聞きません。
学校生活に繋がりそうなことはなんでも褒めておきます。
たとえば、お子さんがランドセルを背負って遊んでいるとします。
そんな時に、「傷ついたりしたらいけないから入学式まで置いときなさい。」なんて注意してしまうと、絶好のチャンスを逃してしまうことになります。
「○○ちゃんもお兄ちゃんだねえ。頼もしく見えるなあ。」
「その中に筆箱とかノートとかが入っていくんだねえ。重くない?」
という風に、褒めたり、予想図が楽しく描けるような声かけをしたり、

などとねぎらったりします。
ポイントは、自尊心をくすぐるということ。
発達障がいを疑われるような育てにくいと感じる子も同じです。
「特性のある子」「こだわりの強い子」と表現されがちですが、【違いの分かる子】なのです。
では、その【違いの分かる子】をどう伸ばせばいいのでしょうか。
ポイントは「好きなことを伸ばす」ということです。
極端に嫌がることは無理強いさせないでくださいね。
服や食べ物などについてどうしても強いこだわり見られるような時は、「発達障がい」を盾に先生にも協力をお願いしてください。
決して、指摘、注意、叱責によって二次障害(※)を引き起こさないよう注意してくださいね。
(※問題行動や精神疾患など、いろいろな形で現れます)
そして、言っても言っても聞かないし、余計にひどくなったと感じたらもう諦めましょう。
「そんなの気にしすぎだよ。大丈夫、大丈夫。」とは言いません。
「○○ちゃんは違いがよく分かるんだねえ。お母さんはそんなのよく分かんない。すごいなあ。どんな風に違うの?」と、興味津々に突っ込んで聞いてみてください。
子どもなりの表現で伝えようとしてくれます。
そこでまた褒めてください。
「素敵な言い方だね。○○ちゃんの気持ちが分かるようだよ。」
「素敵な表現だね。」
「大人な言い方だね。」
というように、褒め方も少しずつ変化させていきます。
子どもが分かる表現から、多様な表現を使うようにし、子どもの言語感覚や表現力を高めるようにしていきます。
褒めるのって難しいですよ!
不登校だった子のお母さんがある日、こんなことを言っていました。
「褒めるとこがないから、一生懸命探してたら注意する暇がなくなりました」と。
その子も学校へ行くようになりました。

▶︎このコラムをはじめから読む
▼理恵先生に直接相談する
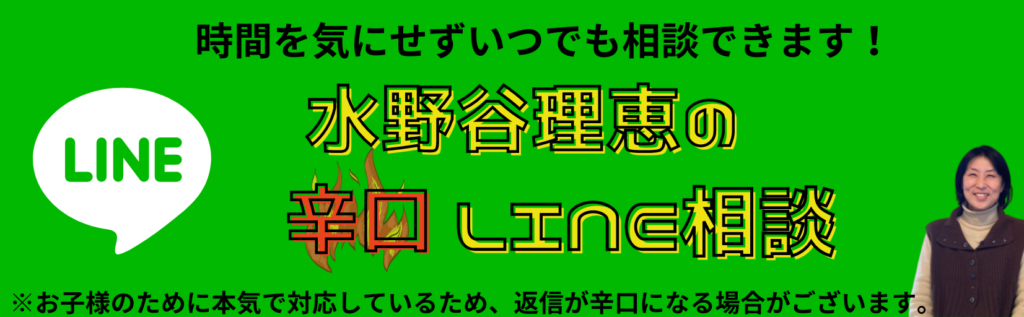
▼理恵先生の子育て講座を受ける