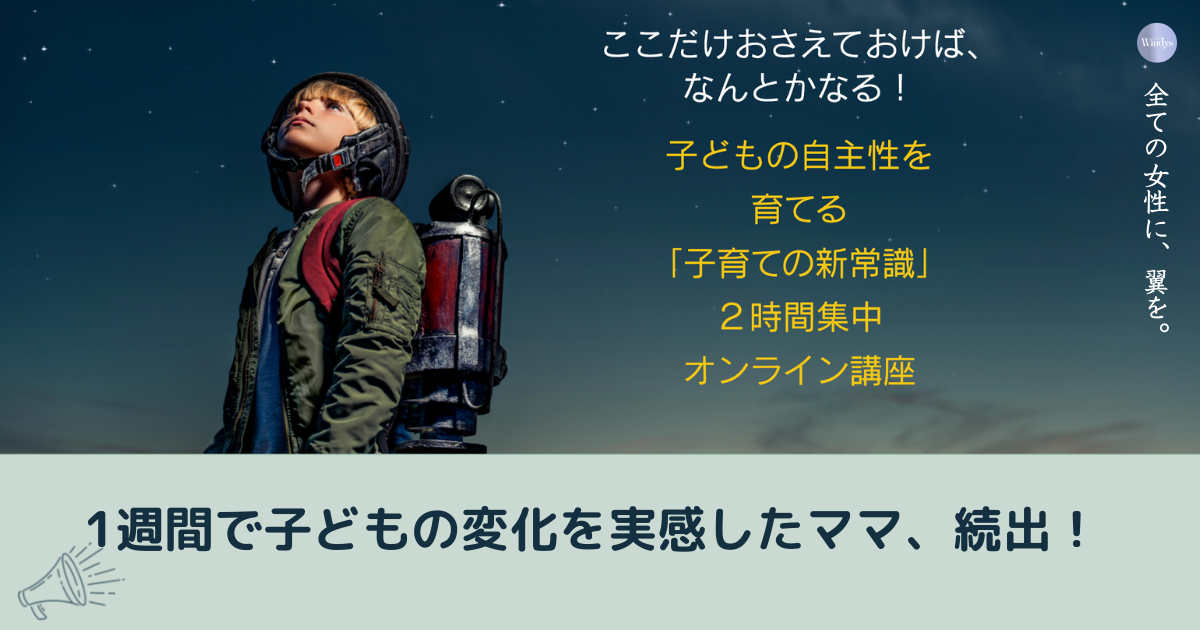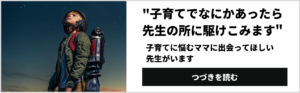〈〈 前回の名(迷)言 『困ったときこそ、「ありがとう」を探そう』
デンジャラスなイメージが強いインドですが、実はこの国、びっくりするほどポジティブで、人の目を気にせず、自分のことが大好きな人が多いのです。
ブッダの言葉よりも、普通のインド人からの名(迷?!)言の方が、今の日本人の悩みを吹き飛ばしてくれるかもしれません。
本日の『普通のインド人の名言』はこちら!

"悩める"子たちがみんな変化する国
コロナの感染が拡大する前、私は会社やグループ向けにインドでのスタディーツアーや観光ツアーの同行をしていました。
インドに「呼ばれて」、インドでの時間を共にしたみなさんとは、きっと日本でご一緒するより何倍も仲良くなれたと思っています。
その中には中学生・高校生のお子さんがいらっしゃる場合もありました。
その子たちは自分から「インドに行きたい」と言ったわけではなく親御さんから「行ってみたら?」と背中を押され、親御さん同行もしくは単身で訪れています。
背景には
「不登校気味で突破口を探している」
「インドとの交流で自分の甘さを感じてほしい」
「将来を考えるきっかけにしてほしい」
など、主にお子さんへの悩みが要因になっていることが多くあります。
「何か変わる糸口になれば」…
そのような親心なのでしょう。
結論からお話しすると、変化をしなかったお子さんは誰一人いません。
もちろんすぐに行動に現れるかは人それぞれですが、消極的な人が積極的になって帰国したり、笑顔が増えたり、将来は海外に関わる仕事がしたいと夢を見つけた人もいます。
なぜそのようなことが起きるのでしょう。
「インドでの貧しさは日本の比ではないから?」
「意見を頻繁に聞かれるから?」
「何でも笑い飛ばしてくれるから?!」

全部正解です。
「彼は頭が悪いわけじゃない。」
でも私が印象に残っているのは、あるドライバーさんがつぶやいたこの一言でした。
発達障害を抱えたお子さんと湖の周りをサイクリングして帰ってきたあと、こう言ったのです。
「この子は頭が悪いわけじゃない。精神病でもない。親が心配しすぎたり、学校が色々なことを押し付けたりするからだ。彼は、もっと誰かと一緒に自由に遊びたい、動いてみたいだけなのに。」
言葉が一切通じなくても、二人は笑顔でホテルに戻ってきたのです。
自分のエゴを突き通したり、間違った世話の仕方をしたりするのではなく、"本当に"目の前の人や動植物が必要としているものを与えてあげる。それが、「しっかり手をかける」ということだと、私もとても勉強になったエピソードでした。

寂しがり屋で笑顔が可愛いインド人。家の牛たちを大事に育てている。交通規則にイレギュラーの多いインドで、逆走・山越えを器用にこなす。でも時々居眠りをして怒られる。(もちろん、眠くなる事情あり)

▼栃久保奈々先生の動画講座セミナー